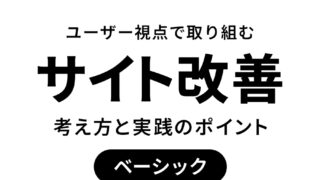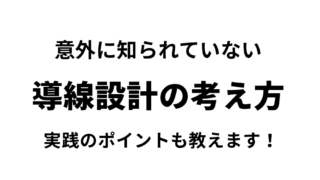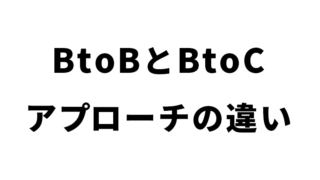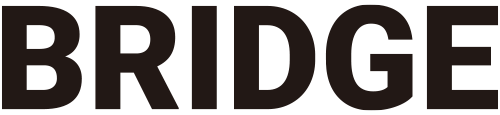橋本です。
4月から6月までの3ヶ月ほど、とあるプロジェクトに参画していました。
九州の企業のサイトの構造設計とデザイン設計のパートを担当させて頂きました。
こちらで一方的に考えて提案をするというのではなく、クライアントのプロジェクトメンバーのみなさんと一緒にあるべき姿を考えるためのファシリテーション的な動きをしながら進めるのが僕のスタイルです。
今回もメンバーでいろいろな考えをシェアをしながら目指したポイントにたどり着くことができました。
WEBのことは一度忘れて顧客のことだけを考えることから始める
WEBサイトを設計するときに大切なのは、WEBのことは忘れて顧客のことを考えることです。この部分をおろそかにして進めていくと、プロジェクトはうまくいきません。
顧客は誰か、その人は何を求めているのかをしっかりと定義をすることが必要です。
すると、WEBサイトを通じて顧客に対して何を提供すべきかがわかるので、サイトの目的や役割、あるべき姿見えてきます。
そのあるべき姿と現状とのギャップを明らかにして、ギャップを埋めるべくWEBサイトの構造、機能、デザインを考えるというのが設計の作業になります。
ここをしっかりやらないと方向性が定まらないので、手戻りも多くなったり、最悪の場合には機能しないサイトが出来上がってしまったりします。
顧客からスタートするとプロジェクトに芯ができる
WEBサイトを構築する、デザインをつくるには、WEBに関する技術的な知識や美しいデザインをつくりあげるスキルだけではなく、顧客のことをよく観察し、想像し、理解する力が必要です。
そして、顧客のことを一番理解しているのがクライアント自身です。
だからこそ、僕はプロジェクトメンバーの皆さんと一緒にクライアントの顧客のことを考える時間を大切にしています。
クライアントにとっては既知のことであったり、当たり前のことだったりもするのですが、場合によっては、そこに思い込みや固定観念などがあったりもするので、一つ一つ時間をかけて紐解いていくこともあります。
紐解いていくプロセスの中でプロジェクトメンバーが合意できれば、そのあとのステップでぶれることはほぼなくなりますし、途中での判断や意思決定が早くなります。
また、WEBサイトが完成して、運用のフェーズに入って後もやるべきことが明確になります。
顧客視点はWEBマーケティングの大前提
顧客視点でつくられたWEBサイトでなければ、当然のことながらマーケティングで活用するのは難しいでしょう。
WEBサイトやコンテンツをつくるには、専門的な知識や技術、デザイン力が必要なのは言うまでもありません。でも、それらは必要条件ではあっても、十分条件ではありません。
マーケットの中心にいるのは、自社ではなく顧客だからです。
関連記事:WEBサイトの活用に必要なのは仮説力
投稿者プロフィール
- プロデューサー・クリエイティブディレクター。早稲田大学政治経済学部卒業。リクルートグループ、オン・ザ・エッヂ、ミツエーリンクス、博報堂アイ・スタジオを経て独立、株式会社ブリッジを設立。徹底的なユーザー視点でのWEBサイトの構築やコンテンツ制作を通じて事業課題の解決を支援している。
最新の投稿