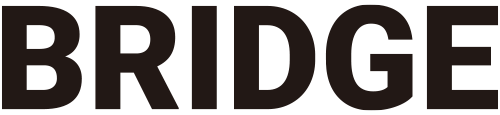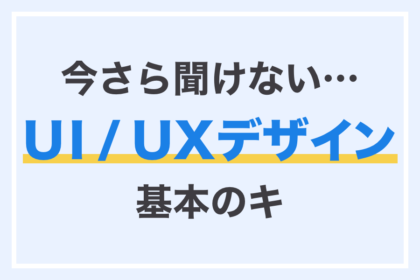WEBコンテンツとひとくちに言っても目的によっていろいろなタイプのものがあります。
集客を目的としたもの、広報や認知を目的としたもの、販売を目的としたものなど、目的が変わればつくり方も変わります。
いま手がけているWEBコンテンツの打ち合わせの中では、内容にとどまらずコンテンツのつくり方についても話をしながら進めています。
自分たちの考えを整理するよい機会でもあるので、こちらにもナレッジとして概要を残しておこうと思います。
フレームワークを使ったWEBコンテンツづくり
僕たちが新しいコンテンツをつくる時には必ずフレームワークをもとに企画をスタートします。
企画というとアイデア勝負みたいに思われがちですが、決してそんなことはありません。
僕自身、かつてはウンウンうなりながらのたうちまわり、突如どこからかアイデアが頭の中に降りてくるのを待つみたいなやり方をしていた時期もありました。そのプロセスこそがクリエイティブ!なんて思っていました。
それでうまくいって誇らしく思ったこともたくさんあったけれど、思い返してみるとやっぱり辛かったような気もします。いろんな意味で若かったんですね…。
そんな経験をしながらたどり着いたのがさまざまなフレームワークの活用です。
メンバー間で共通言語となっているフレームワークを活用することで属人的なアプローチになることなく、課題を共有しながら進められます。
もちろんアイデアはとても重要です。アイデアこそが違いつくるからです。
全体の大きな流れはフレームワークをもとにロジカルに組み立てていきます。盛り込むべき要素をもとに材料を集めながら進めます。
ベースとなるフレームワークをもとに大まかなストーリーをつくり、細かなところにさアイデアのフレームワークを使いながらディテールをつくっていきます。
WEBコンテンツづくりで大切なのは最初の質問
フレームワークを活用するにあたって、もう一つ重要なものがあります。
それは、
「これはなんですか」
という質問に端的に答えるということです。
今からつくる(考える)コンテンツとは「そもそもなんなのか」をシンプルかつ具体的に表現するものです。
社内では最初の質問なんて呼んでいます。
説明的なもの、修飾的なものを省いてコンテンツのポイントを明らかにするので、ストーリーの組み立てやアイデアのベースにもなりますし、ズレなく進んでいるかのチェックにも使います。
質問に対する納得がいく答えが得られれば向かうべき場所、表現すべきものが見えます。
シンプルかつ具体的であることが重要です。
アイデアは思いつきではなくつくりこんでいくもの
アイデアもまたフレームワークによってつくり込んでいけるものです。
僕がコンテンツづくりのバイブルとしている「アイデアの力」という本の中では、記憶に残るアイデアの条件として
- 単純明快である
- 意外性がある
- 具体的である
- 信頼性がある
- 感情に訴える
- 物語性がある
の6つの原則を紹介しています。
僕たちの心を動かし、記憶に残るWEBコンテンツやメッセージはこれらの原則を満たしていることに気がつきます。
アイデアというと、この6つの原則の中で「意外性がある」に目がいきがちなの気がしますが、必要条件ではあっても十分条件ではないということですね。
アイデアマンというのは天才的なひらめきをする人ではなく、これらの原則にもとづいてスピーディーにアイデアを出して形にする人のことなんだなと理解しています。
ブリッジはアイデアマンならぬアイデアカンパニーとして記憶に焼きつくWEBコンテンツづくりに取り組んでいます。
投稿者プロフィール
- プロデューサー・クリエイティブディレクター。早稲田大学政治経済学部卒業。リクルートグループ、オン・ザ・エッヂ、ミツエーリンクス、博報堂アイ・スタジオを経て独立、株式会社ブリッジを設立。徹底的なユーザー視点でのWEBサイトの構築やコンテンツ制作を通じて事業課題の解決を支援している。
最新の投稿