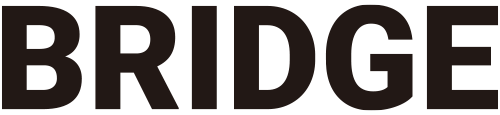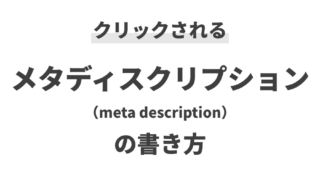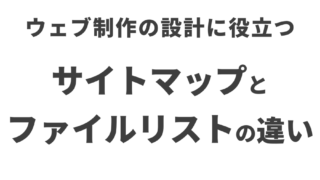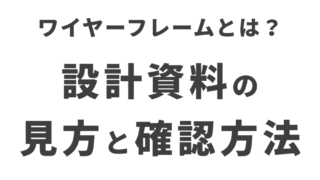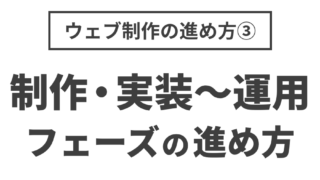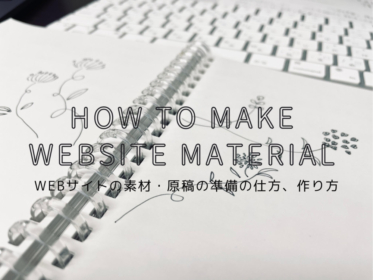自社のホームページから採用につながるような方に直接応募してもらうために必要なのが、サイト上に「採用コンテンツ」を作ることです。
また、すでに募集要項を書いた採用ページや採用サイトを持っているけど、応募が来ない…という企業様もいらっしゃらないでしょうか。
その原因は
- 求職者が求めている情報を届けることができていない
- 届けられていたとしても他社との比較で負けてしまう(これはその人の優先順位の問題なので変えることができない)
ことが考えられます。
改善するべきは、前者の「求職者が求めている情報を届けることができていない」です。
つまりは、「興味があり採用ページを見てくれているのに知りたい情報が少なくて興味を持ってもらうことが出来なかった」ケースと
「採用情報がそもそもなくて、求人自体の認知ができていない」ケースです。
これらを解決する手段が 「採用コンテンツ」です。
採用コンテンツは以下の3つのステップで作ることができます。
- ターゲットの明確化
- 打ち出すコンテンツを考える
- どう打ち出すかを考える(コンテンツ内容、写真、動画等)
この記事では実際に、上の3ステップを使って「新卒採用」と「中途採用」2つのパターンを考えてみようと思います。
ちなみに、私は前職、新卒・中途採用の転職エージェントとして働いていたので、実際に求職者にインタビューしておりました。
本記事では、その時の経験もふんだんに盛り込んでおりますので、参考になれば幸いです。
※下記はあくまで一例です。
ターゲットを明確化するには?
【新卒採用の場合】
- 会社の風土とマッチする学生はどんな学生か考える
- 専門職であればどの程度のスキルがあればよいか明らかにする
【中途採用の場合】
- 採用したい部署の求めているスキル×転職市場にいる人
- 自社にはどんな人だとマッチするのか、価値観や志向性を考える。
(どんどん新しいスキルを学びたい人、決まったことをきっちりこなしワークライフバランスを整えたい人…等)
※ターゲットの考え方については本題から離れてしまうためこちらでは省略させていただきます。
打ち出すコンテンツを考える
ターゲットの悩みを考える
【新卒採用の場合】
- 自分が働くイメージが沸かない
- その会社に入った後のどんな社会人になっているのか想像もつかない。
- 親を安心させたいから会社の存在意義、社会への貢献度が知りたい。
(特に最近はSDGsに関する関心を持つ学生が増えている)
- 会社のビジョンなど情報が大きすぎて具体的に何をやるのかわからないなど
【中途採用の場合】
- 年収アップしたい
- 新しい経験を積みたい様々なことにチャレンジができる
- 人間関係の悩み
- 評価が不透明→明確な評価軸がある
- ワークライフバランス(残業を減らしたい、妊娠出産などライフステージ)
など
どんなことを伝えれば良いのか
【新卒採用の場合】
- 働いているイメージの沸く情報
- 会社の存在意義、社会への影響、会社の規模感
- 具体的にどんな仕事をするのか
- どんなふうに成長できるか
- どんな先輩が活躍しているか
- 成長性
- 安定性
など
【中途採用の場合】
- キャリア形成と年収例、どんなスキルを求めているか
- 様々なことにチャレンジができる
- 風通しのいい社風、前向きな社員が多い
- 明確な評価軸がある
- 平均残業時間や残業を減らすための取り組み、福利厚生やキャリアの選択肢があること
など
POINT:採用活動はBtoBの考えの方がマッチする
求職者に応募してもらうためのマーケティングの考え方として、求職者は個人なので、BtoCじゃなないの?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ご自身が転職活動をされているとしたら、転職サイトや企業の採用ページを見て魅力を感じられても、"即決"で会社を選ぶのではなく、転職先"候補"にいれるだけだと思うんです。
求職者にとっての会社選びには、「可愛いから買う!」といったBtoCのようなマーケティングよりも、冷静な判断が入るBtoB寄りの考え方の方がマッチすると考えます。
POINT:"なんとなく"と"それっぽく"が一番危険
「だいたい採用コンテンツって、"一日の流れ"とか"社員インタビュー"とかがあったらいいんでしょ。」とそのまま進めていくと、
作ったコンテンツに根拠がないため、結果検証も出来なければ、誰にも刺さらない可能性もあります。
採用コンテンツの例
募集要項、ビジョン・ミッション、事業紹介、代表メッセージ、職種紹介、社員紹介、FAQ、会社説明会の情報、インターン実施の有無
その他にも、社員インタビュー、キャリアパス、評価制度(概念や年収例など)、メンバー紹介、オフィス紹介、企業文化や歴史の紹介、企業の価値観、社員ブログ…など
一例ですが、こんなにもあるんです。
後は、ターゲットごとの伝えたい内容に合わせて組み合わせを選んでみるのが良いと思います。
例えば、新卒採用の場合、以下のように割り振ってみました。
- 働いているイメージの沸く情報
→先輩社員の一日、社員ブログ、オフィス紹介
- 会社の存在意義、社会への貢献度
→ビジョン・ミッション、代表メッセージ
- どんなふうに成長できるか
→職種紹介、社員インタビュー
- どんな先輩が活躍しているか
→社員インタビュー、メンバー紹介
- 会社の規模感
→企業文化や歴史の紹介、事業紹介
- 成長性
→ビジョン・ミッション、事業紹介
- 安定性
→ビジョン・ミッション、事業紹介
他にも、会社説明会の情報、インターン実施の有無はあったほうがいいですね。
社員インタビューも記事にするのか、動画でインタビューするのかなど手法がたくさんあります。
しかしこれらを全部作るとなると、予算の兼ね合い も出てくると思います。
また、就活生もすべてのページをしっかり読んでくれないケースもあるのでなるべく端的にアピールする必要があります。
そのため、次は優先順位を決めてどの採用コンテンツを作るのか検討してみましょう。
どう打ち出すかを考える
定形がないからこそ、グラフィックを最大限活かしたい
作る採用コンテンツが決定したら、最後のステップ、「見せ方」を考えましょう。
用意することとしては、写真素材、(必要に合わせて)動画、掲載情報の原稿になります。
準備するのはどれも一筋縄では行かないと思います。
しかしここを乗り越えられたら採用コンテンツは完成です!
準備するのは大変ですが、自社サイトでの採用コンテンツでは、求人サイトと違い採用ページや採用サイトでは雛形にとらわれず作り込むことができるため、求職者に自社の魅力を最大限アピール出来るチャンスです。
そのため、写真・動画などのクリエイティブはこだわりたいところ。求人サイトではなかなか伝わりきれない自社の魅力を作り込んでいきます。
弊社にて採用ページを制作させていただいた際は、写真撮影からインタビュ動画撮影などもご準備させていただき、クリエイティブにも力を入れております。
社内のリソースが足りないときはお声がけください。
志望度は求職者の持つ情報量に紐づく
最後に、採用活動するのにあたってぜひ覚えていて欲しい言葉が上記のものです。
あなたが、「久しぶりにある友人とゆっくり喋りながら飲みたい」時、
グルメ予約サイトの検索結果にA店とB店が出てきました。
A店のページ
- 文字だけのメニュー
- 口コミも少ない
- 席数や店内の様子が分からない
B店のページ
- 写真のついたメニュー
- 口コミが多い
- 開放感がある店内
- 仕切りのある座席
このような場合、ほとんどの方が「久しぶりにある友人とゆっくり喋りながら飲みたい」ニーズを満たす情報が掲載されているB店を選択すると思います。
求職者も同様実態がわからないからこそ、候補に入っている企業の中で優先順位をつけるなら 情報量が多い順に志望度が並びます 。
(もちろん、もともと志望度が高いから情報をとってくるということも含まれています。)
採用コンテンツは適切な情報を届けることさえできれば、求職者にとっての志望度を上げるために有効な手段です。
投稿者プロフィール


- プロデュースチーム ディレクター。早稲田大学人間科学部卒業。大阪出身。