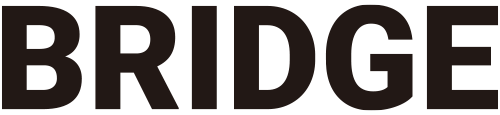ホームページをより効果的に改善したいと考える中小企業のWeb担当者や経営者にとって、ユーザーの行動をどう捉えるかは非常に重要な視点です。
今回ご紹介するのは、「ユーザー行動」を観察することで、ユーザーの本音や潜在的なニーズを読み取り、それをホームページ改善に活かすというアプローチです。これはデザイン思考における「観察」の視点を応用したものであり、ユーザー中心の発想を深めるうえで非常に有効です。
ユーザー行動につながる「合理性」を理解することがホームページ改善の第一歩
合理性とは、ユーザーが自分の目的を達成するために、最も効率的・効果的だと考える手段を選ぶという行動原理のことです。言い換えれば、ユーザーは常に「自分にとっての最適解」に従って行動しているのです。
企業としてホームページを運用する側は、「こう見てほしい」「こう使ってほしい」という意図をもとに情報設計を行いがちです。しかし、実際のユーザーは、自分の目的を達成するために、最も効率的・効果的だと考える行動をとります。
ですので、企業側の合理性ではなく、ユーザーの合理性にもとづいて情報設計や導線設計を行えば、改善につなげることができます。
この「合理性の違い」を理解せずにホームページを改善しても、成果につながる可能性は低く、むしろ的外れな施策となってしまうことすらあります。
だからこそ、ユーザーの合理性を深く理解することは、ホームページ改善において極めて本質的な出発点になるのです。
デザイン思考で「ユーザー行動」からニーズを探る
デザイン思考は、「共感」「観察」「アイデア発想」「プロトタイピング」「テスト」の5つのステップで構成されるユーザー中心の問題解決手法です。なかでも最初のステップである「観察」は、ユーザーの行動から潜在的ニーズや課題を掘り起こす上で非常に重要なフェーズです。
特に注目すべきなのは、企業が意図していないような行動、いわゆる「極端なユーザー行動」です。
たとえば、
- ページのメニューを無視してURLを直接入力してくるユーザー
- 問い合わせフォームの注意書きを読まず、営業提案を送り続ける営業担当者
- ナビゲーションを嫌って、トップページから即離脱するスマホユーザー
これらの行動は、表面上は「ルールを守っていない」「正しく使っていない」と見えるかもしれませんが、裏を返せばそれぞれのユーザーにとっての合理的な選択なのです。
営業メールの例に見る、合理性のズレと改善のヒント
たとえば、自社ホームページに「営業目的での問い合わせはご遠慮ください」と明記しているにもかかわらず、営業メールが届いてしまうケース。
ここには、企業と営業担当者の合理性の違いが存在します。
企業側の合理性
- 不必要な営業メールは時間の無駄であり、本来対応すべきユーザーへの対応が遅れる
- 問い合わせフォームに営業目的のコンバージョンが含まれると、データが正確に分析できず、マーケティング施策の精度が落ちる
営業担当者の合理性
- 成果を出すために、少しでも接点を持てる可能性のあるチャネルを使いたい
- 担当者にメールを読んでもらえればチャンスが生まれると考えている
こうした合理性のズレは、ユーザーと企業が異なるゴールを持っているために発生します。
このような状況に対して、デザイン思考を活用すれば、単に「禁止」とするのではなく、双方にとって納得のいく着地点を設計することができます。
たとえば、
「営業目的の方はこちら」という専用のフォームを用意することで、企業側はデータの精度を保ちながら、営業側にも情報提供の機会を残す
という改善案が生まれます。
これは、ホームページ改善におけるデザイン思考の具体的な成果の一例です。
ホームページの裏にあるユーザー行動の「見えない合理性」を探る
ユーザーが想定通りに動かない理由はさまざまです。たとえば、
- スマートフォンではメニューが開きづらい → 離脱してしまう
- フォームの入力項目が多すぎる → 問い合わせを断念する
- よくある質問やサポート情報が探しにくい → 結局電話してしまう
これらもすべて、ユーザーの合理的な選択によって起こっている行動です。
「なぜそういう行動をしたのか?」を問い直すことで、私たちはユーザーが何を求めていて、どこに課題を感じているのかを発見できます。
ホームページ改善にデザイン思考を活かすために
- ユーザーの行動に先入観を持たないこと
- 企業側の正解ではなく、ユーザーにとっての正解を探ること
- ユーザーの合理性にこそ、イノベーションのヒントがあること
これらの視点を持つことが、ホームページの改善においてとても重要です。
デザイン思考を通じて観察と共感を繰り返せば、ただ機能を追加したり、見た目を整えるだけではない、本質的な改善につながっていきます。
合理性を読み解くことが、次の改善の起点になる
ユーザーの合理性を理解することで、これまで気づけなかった課題やニーズが浮かび上がってきます。ユーザーの視点に立って思考し、改善のヒントを得る姿勢こそが、デザイン思考の本質であり、ホームページ改善における大きな武器になります。
関連リンク
投稿者プロフィール


- プロデューサー・クリエイティブディレクター。早稲田大学政治経済学部卒業。リクルートグループ、オン・ザ・エッヂ、ミツエーリンクス、博報堂アイ・スタジオを経て独立、株式会社ブリッジを設立。徹底的なユーザー視点でのWEBサイトの構築やコンテンツ制作を通じて事業課題の解決を支援している。
最新の投稿